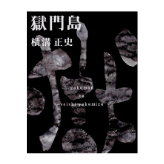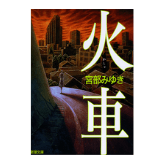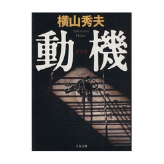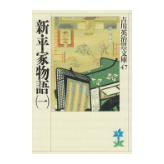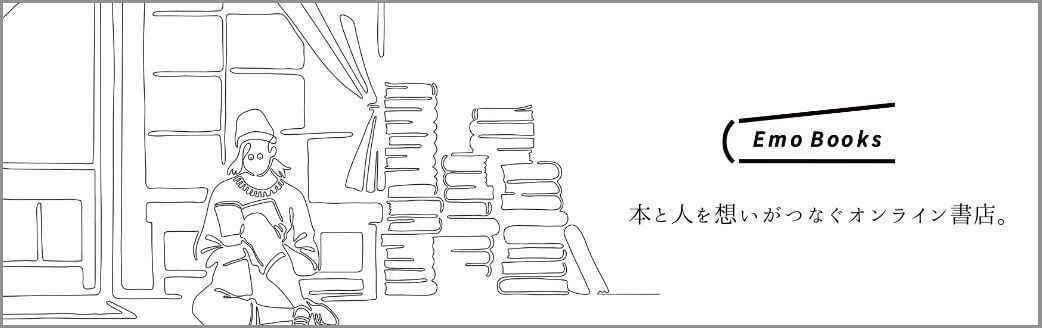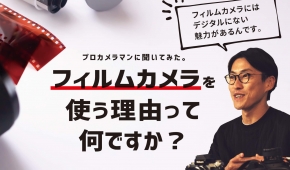2021.01.19 Tue
作家・越尾圭さんが選ぶ5冊の本┃人生を共に歩んだ「ミステリー小説家をつくった本」

人生で特別な5冊を紹介してもらう連載企画「5冊の本」。
今回お話しを伺ったのは、愛知県東浦町出身のミステリー作家・越尾圭さん。
会社に勤めながら執筆活動を続け、2018年に第17回「このミステリーがすごい!」大賞・隠し玉に著書『クサリヘビ殺人事件―蛇のしっぽがつかめない」が選定され、同年に作家デビューを果たしました。

¥792
発行/宝島社
著者/越尾 圭
「学生のころから創作活動をしていたものの、本格的に作家を目指したのは社会人になってからですね」。
そう話す越尾さんが、どのようなきっかけでミステリー作家を目指したのか。また、ミステリー小説を書く上でどんなことを大切されているのでしょうか。
越尾さんが作家デビューを果たすまでに読んできた印象深い5冊を紐解き、「ミステリー小説家をつくった本」として紹介していきます。

|
この記事のライター/水野史恵(エディマート) エディマートに所属し、編集や執筆の業務を担当。東海地方を中心とした情報誌や観光ガイドブック、新聞記事などを制作している。出身は越尾さんと同じ東浦町。読みだすと止まらないという理由から、ミステリー小説は休日にじっくり読むのが好き。『S&Mシリーズ』に代表される森博嗣作品のファンである。 |
目次
1.作家デビューまでの道を共に歩んだ作品

「小さいころは手塚治虫や藤子不二雄など、マンガばかり読んでいました」。
越尾さんは、自身の読書遍歴をこう振り返ります。小学生のころはマンガに夢中の日々を過ごし、中学生のころは歴史小説に没頭。ミステリー小説とは無縁の生活を送っていたとか。
そんな越尾さんが初めて出合ったミステリー小説としてあげたのが、『獄門島(角川文庫/横溝正史)』でした。
『獄門島(角川文庫/横溝正史)』

『八つ墓村』『犬神家の一族』を代表とする、横溝正史の推理小説「金田一耕助シリーズ」。『獄門島(角川文庫/横溝正史)』はその2作目にあたり、雑誌『宝石』に17回連載されたエピソードをまとめた小説です。連載当時である1947年1月から1948年10月までの時代を表すかのように、作品全体に敗戦直後の混乱が描かれているのも特徴の一つ。
「3人の妹たちが殺される。おれの代わりに獄門島へ行ってくれ」という戦友・鬼頭千万太から託された遺言を頼りに、金田一が瀬戸内の孤島を訪れるシーンから物語ははじまります。島に到着した金田一は3人の妹と出会い、そののちに千万太の葬儀が営まれることに。そしてその夜、末妹の花子が行方不明となってしまうのでした。
後世の推理作家に多大な影響を与えた、ミステリーの金字塔とも呼ばれる本書。
日本推理作家協会の会員が選ぶ、推理小説のオールタイムベスト選定企画「東西ミステリーベスト100」の国内編で、1985年版と2012年版の1位に選出されるなど、作家からの評価も高い作品です。
そんな『獄門島(角川文庫/横溝正史)』は、越尾さんにとっても強く記憶に残る一冊だったそうです。
「正義感の強い清水巡査や、まるで子どものように立ち振る舞う三姉妹など、金田一耕助以外のキャラクターも個性的で、読み進めるにつれて作品の世界に引き込まれていきました。何より“見立て殺人”が当時のぼくにとって衝撃的でしたね」

「犯人のトリックと動機はミステリー小説の醍醐味。この本の見立て殺人というトリックと、田舎独特の風習や因縁が複雑に絡んだ動機、どちらも独創的だと感じました」。
獄門島の舞台は孤島。田舎らしいのんびりした空気感が流れつつも、封建的な古い因習が残る排他的な土地柄であることが作中で上手く描かれています。
驚くことに横溝正史自身は島の風習について見識はなく、知人から聞いた話をもとに構想を広げていったそうです。
「時代背景から舞台まで、設定のほとんどが事件の真相に少なからず結び付いているんですよね。犯人のつぶやいた言葉の意味が解き明かされた時にとくに衝撃を受け、この設定だからこそ生きたのかなと思います」。
その記憶は、作家を目指すことになった20年後にも鮮明に残っていたそう。そんな因果もあり、越尾さんが初めて応募した賞はまさに「横溝正史ミステリ大賞(現:横溝正史ミステリ&ホラー大賞)」でした。初応募ながら一次選考を通過したことが自信となり、越尾さんは本格的に作家を志すことになりました。
『火車(新潮社/宮部みゆき)』

賞に応募するようになり、本腰を入れてミステリー小説の執筆を進めた越尾さん。それと並行して、これまでは手にとってこなかった、さまざまな作品を意識的に読むことにしたそうです。
「このミス」の第8回大賞作品『さよならドビュッシー/中山七里』をはじめ、『十角館の殺人/綾辻行人』『13階段/高野和明』などを精読する中で、とりわけ印象的だったのが『火車(新潮社/宮部みゆき)』だったと話してくれました。
発刊当時に社会問題となっていた、消費者金融のあり方をテーマとした本書。
謎の失踪を遂げた和也の婚約者・彰子を探し出して欲しいという依頼が、刑事である本間俊介に届いたことを発端に、物語の幕が開きます。彰子を追い求めるうちに、彼女が過去に自己破産をしていたことが発覚。さらに和也と婚約をした彰子は、偽物のなりすましではないかという疑念が浮かび上がったのです。
「ミステリーに社会問題を絡ませた作品が好きなので、この作品を手に取りました。『火車(新潮社/宮部みゆき) 』は約30年前の作品なので利息のシステムや個人情報の扱いは今と違うものの、カード破産という社会問題は30年経った今も存在しています。そんな視点からも、社会問題を取り扱った話は興味深いなと思います」。
日本に根深く残る社会問題を描いた本書は、メッセージ性だけでなく、ミステリー小説として参考になるポイントも多くあるそう。
「ストーリー構成がうまいんですよね。犯人と思われる人を追っていくと、途中で手掛かりが途絶えてしまう。『じゃあこれからどうなるんだ』と気になり、その先を読みたくなる。作品を読んでいて“ページをめくらせる力”を感じました」。

そしてこの小説のキーポイントは、ラストシーンであると越尾さんは話します。
本を読んだあとの印象形成において、ラストシーンは重要です。しかし世の中にミステリー小説は数多くありますが、“印象に残る結末”を見事に描いている本は一握りともいえるでしょう。
「ラストに判明する、あるキャラクターの真意には目を見張りましたね。ミステリー小説をたくさん読んでいると、犯人とかラストシーンとかを思い出せなかったりするけど、この本の最後のシーンははっきり覚えています。
結末のラスト一行がまた良いんですよ」。
“美しくも悲しい”と評されるラストシーン。なぜ印象的なのかは、ぜひ実際に読んで、感じ取ってみてくださいね。
そして次に紹介してくれた小説は、『動機(文藝春秋/横山秀夫)』。この本にも、越尾さんならではの読み取り方がありました。
『動機(文藝春秋/横山秀夫)』

ミステリーを構成する要素は「事件」「アリバイ」「トリック」「推理」が挙げられますが、越尾さんはとくに重要なのが“動機”だと話します。
本書には動機にまつわる4つの短編が収録されていますが、中でも越尾さんが強く共感したのが表題作である『動機』だったそうです。
「県警本部警務課の企画調査官である貝瀬の提案で、警察手帳を一括保管する案を採用。このことを皮切りに物語は動き出します。刑事部の猛反発を押し切って試験的にその案が運用されますが、なんと保管している
容疑者候補には動機がまったくなく、成す術がない。犯人が見つからなければ発案者である貝瀬自身の立場が窮地に立たされるという状況のなか、彼はどのようにして犯人を探し当てていくのか…。
「犯人がなぜ事件を起こしたのか、そこに納得できないとストーリーは成り立たない。仮に犯人が(相手は)誰でもよかったと言っても、『誰でもよかった』に至るまでの過程は気になりますよね。でもこの作品は動機の見当が付かないから、展開が予想できないんですよね」
私が今まで読んできた小説を思い返してみると、確かに犯人には確固たる動機があることに気付きました。
例えば、『そして誰もいなくなった/アガサ・クリスティー』では行き過ぎた正義感を持ってしまった元判事のように、『告白/湊かなえ』では娘を級友に殺害された教師のように。多くのミステリー小説で描かれる犯人には、誰もが抗えない“動機”を抱えて犯行に及んでいます。

動機が見つからないまま物語は進んでいきますが、最終的に犯人は確かな動機を抱いていることが判明。越尾さんはその動機に共感し、理由に胸を打たれたそうです。
「警察内部のいざこざが進み、緊張感が高まっていく構成も面白いのですが、やはり最後のシーンですね。予想できなかった犯人の動機が明らかになるのですが、それが自分のためではなく、誰かのためにやったことだったんです
越尾さんは自身の著作でも、“動機”をどう表現するのかを大切にしているそうです。
「どんな犯人であろうと必ず動機はあります。動機に共感してもらうために、犯人の人物像が浮かび上がるようなエッセンスをストーリーの中にそれとなく散りばめさせておく。そうすることで、読者が共感や納得がしやすくなるんです」。
越尾さんは今回のインタビューをきっかけに、久しぶりに『動機』を読み直したそう。以前読んだ時から年齢を重ね、40代だからこそ感じたことも。
「主要人物と同世代になったことで、キャラクターが抱く思いが余計に刺さりました。みなさんに読んでほしい本ですが、ぼくと同世代の人にはとくにおすすめですね」。
2.自分の歩んできた“平成”を振り返る
「ミステリーをテーマに5冊の本を選んでほしいといわれたときに、自分の人生の大半を占める“平成”にちなんだ本を選びたいと思って、この本をセレクトしました」。
1989年から30年あまり続いた平成の時代。
ガラケーからスマートフォンへと変化した携帯電話の普及や、今なお進化するインターネットの台頭。阪神・淡路大震災、東日本大震災といった大規模災害の発生。地下鉄サリン事件に代表される衝撃的な事件が起こる一方で、新たなカルチャーも続々誕生し、“J-POP”という言葉が浸透したのもこの時代です。
越尾さんは、そんな平成という時代をテーマにした作品を紹介してくれました。
『平成ストライク(角川文庫)』

『平成ストライク(角川文庫)』は福知山線脱線事故、ネットで起こった炎上事件、児童虐待、渋谷系、東日本大震災といった、平成の時代に実際に起きた事件・事象をテーマに描いた作品集。
「平成という時代を振り返りつつ、作品を楽しめるのがこの本の魅力ですね。例を挙げると」。
自分が生きた時代に起こった事件や、新しく誕生した事象を忘れたくない、という思いで本書をセレクトした越尾さん。
自身も実際に起こった事件をモチーフにして、作品を執筆した経験もあるそうです。
「ある鉄道が正面衝突をする事故があって、当時の状況や原因を調べて忠実に描きました。実際の事件を取り上げると、読み手側もシーンを想像しやすくて入り込みやすいですよね。あとは、有名な事件を取り上げたからこそできる、トリックの裏切りがあったり…」。
実在した事件をモデルにすることでリアリティを感じ、読者である私たちも実際に事件が起きているかのような感覚を味わえます。有名な事件であれば、メディアで報道された様子の描写を盛り込むことで、臨場感を感じることも。そこに、筆者独自の脚色や結末が加わることで、より魅力的な作品になるのかもしれません。

本書はアンソロジーと呼ばれる作品集であるため、複数作家の作品が一度に読めることも魅力の一つ。
アンソロジー (Anthology) とは、文学作品を一つの作品集としてまとめたもの。多くの場合、主題や時代など特定の基準に沿ったものが複数の作家の作品から集められる。小説など文学作品に限らず、漫画、コミックなどでも使用される。
「9つもの短編が載っていて、さまざまな作家さんの作品が気軽に読めるのがうれしいですよね。ほかの作家さん目当てで購入したら『意外とこの人面白いぞ』と発見があるかもしれませんよ」。
普段選ぶ本が固定されている人にとって、新しい出合いのきっかけになりうるアンソロジー。
例えば、幸せをテーマにしたアンソロジー『Happy Box(PHP文芸文庫)』では、伊坂幸太郎や真梨幸子などペンネームに「幸」の付く5人の人気作家の作品を収録。ほかにも、前の筆者がお題とともに、バトンを渡す相手をリクエストするリレーアンソロジーの『9つの扉(角川文庫)』など、個性豊かなアンソロジー作品が多数出版されています。
みなさんもぜひお気に入りのアンソロジーを見つけてみてください。

3.諸行無常を描きながらも深い愛情が伝わる
インタビュー中は常に穏やかな表情で応じてくれた越尾さん。言葉の端々から優しい人柄がにじみ出ていました。
そんな越尾さんが最後に紹介してくれたのが、人生の転機を支えてくれた一冊『新・平家物語(講談社/吉川英治)』です。
『新・平家物語(講談社/吉川英治)』

『平家物語』を中心に『保元物語』『平治物語』『義経記』『玉葉』など複数の古典をベースにして、源平両氏や奥州藤原氏、公家などの盛衰を描いた長編作品である本書。
1950年から1957年まで「週刊朝日」に連載されたのち、全16巻の文庫版が出版されました。
歴史小説は基本的に史実に基づき、それを追う形式で執筆されるものですが、『新・平家物語(講談社/吉川英治)』で着目したいのは“史実の裏側”だといいます。
「史実は動かせない事実ではあるんですが、事実の裏側、つまり書かれていない部分は必ずあるもの。それに、史実自体も文献によって変わったりしますよね。だから想像する余地はいくらでもあるんです」
例えばこの本では、歴史上には存在しない阿部麻鳥というキャラクターが登場しています。
「全16巻という超大作の中で、一番広く長く登場しているのがおそらく阿部

そんな『新・平家物語(講談社/吉川英治)』を読むのは、決まって人生のターニングポイントだったそうです。
「この本を初めて読んだのが10代のとき、次に20代、その次は30代と10年おきくらいに。ちょうど自分の人生の転機にあたる時期。そういうタイミングで読み返していますね。」。
また、読んだ時期によって、物語の見え方や受け取り方も変わったそう。
「20代のころは若い武将の立場・考え方に近かったんですが、今の年になって読むと彼らの親目線で読んでしまいますね。そうすると戦地へ赴く子どもたちへ抱く、親の愛情が伝わってきます。儚さや虚しさだけじゃなくて、きちんと人間の温かさも描かれている。だからこそ、何度も読み返してしまうんでしょうね」。
また越尾さんは、「読む度に新しい発見があります」ともいいます。仕事や生活が変化をしても、ずっと変わらずに本書を大切にしてきたので、そんな発見ができたのではないでしょうか。
コロナ禍において刻々と変化する日々を過ごす中、未来を見据えることは簡単ではありません。
しかし、諸行無常を説いた『新・平家物語(講談社/吉川英治)』とともに長い旅路を歩むことで、新しい気づきや学びと出合えるのではないでしょうか。
4.おわりに

今回、越尾さんは「ミステリー小説家をつくった本」をテーマに5冊の本をセレクト。
インタビューが始まると「今回のために本を読み返してきましたよ」とポツリ。その心遣いにうれしく思い、話を聞く中でも「改めて本を開くと、初めて読んだときの印象と変わりますね」と笑顔を見せてくれました。
人は年を追うごとに周りの環境が変わり、人生経験を積み重ねていきます。一度読んだ本でも時の流れによって、感動し、考え込み、思い抱く印象は変化するものではないでしょうか。
人生の道程とともに、物語に寄り添い続けた越尾さんが示してくれた“共感”というキーワード。まさに、新しいミステリーの楽しみ方を教えてくれた気がしました。
多様な作風があり、テーマや志向性もさまざまなミステリー小説。
「なぜ犯人に共感できるのだろうか?」「ラストシーンが鮮烈に残るのはなぜだろうか?」。これまでとは違った視点で、新たなミステリー小説を体験してもらえたらうれしいです。
写真=山本 章貴/取材協力=東浦町中央図書館
関連記事
新着記事
人気記事
お問い合わせ
お仕事のご相談や、採用についてなど、
お気軽にお問い合わせください。