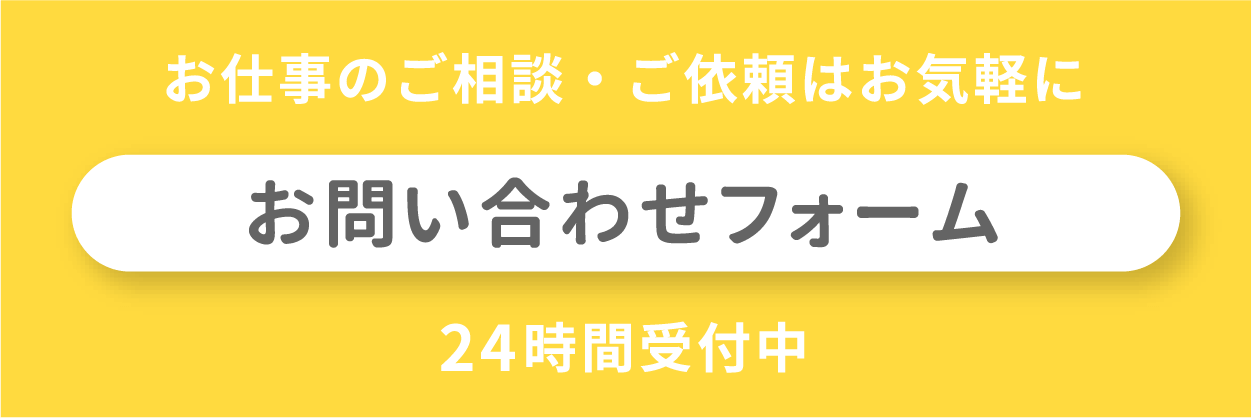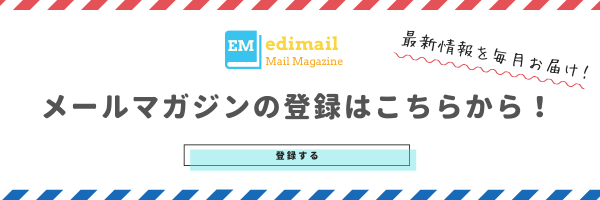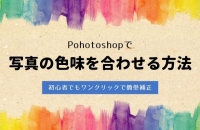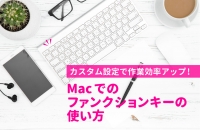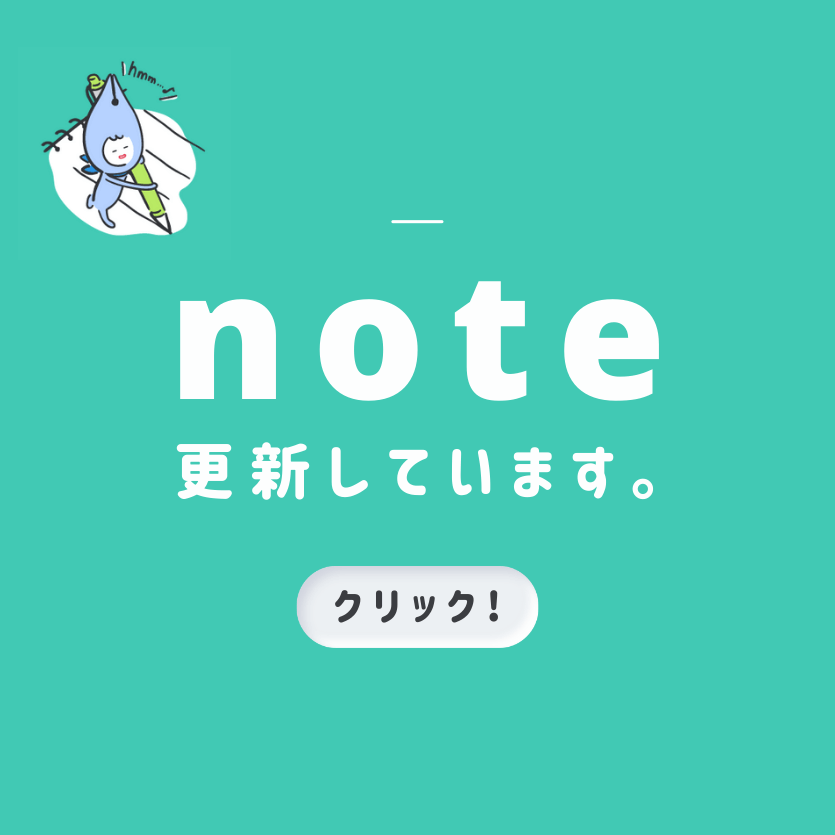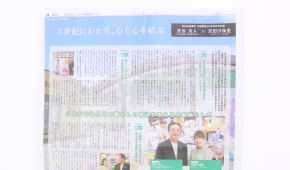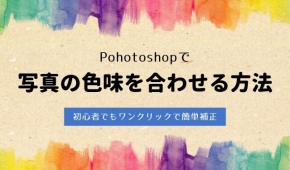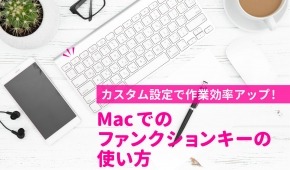2021.03.26 Fri
対談記事のつくり方とは?大切な台本づくりや当日の進行、「伝わる」原稿のまとめ方をレクチャー

「代表が社内報で対談をやりたいと言い出した。どうすれば…」
「インタビューはできるが、対談となると準備が大変そう…」
ある人の「想い」を発信する際に、インタビューによる記事づくりは常套手段です。自分たちでインタビューを行い、コンテンツ化した経験がある人も多いのではないでしょうか。
二者による「対談」、三者による「鼎談」、それ以上の「座談会」は、自分では伝えにくいことがクロストークにより伝えやすくなったり、登壇者のブランド力により自社のステージを上げたりと、インタビューとは違うメリットがあります。
今回の記事では、
・原稿作成と同じぐらい大切な事前準備
・対談をスムーズに進行する当日の動き方
・対談記事の仕上げ方
・対談記事の実例
を、実践を重ねてきた経験をもとに解説していきます。
内容が濃く、読み応えのある対談記事は読者へのリーチが高く、登壇者も満足すれば、新たな展開も期待できるかもしれません。この記事を読んで、クオリティの高い対談を実現させましょう。
1.対談前までにやっておきたい構成案や台本づくり
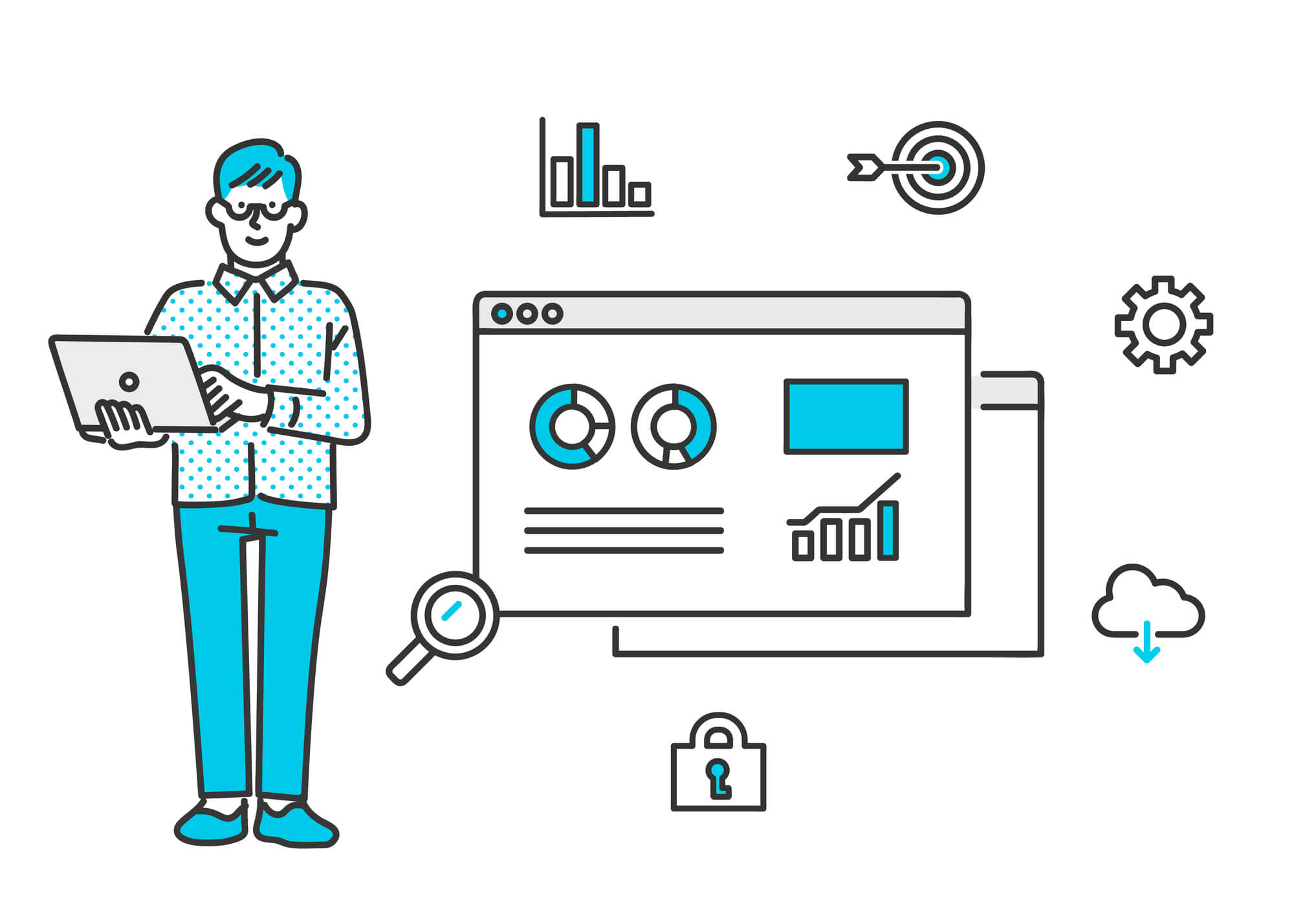
対談記事の成否は、事前準備にかかっているといっても過言ではありません。インタビューの場合の事前準備は、質問案を作成して媒体社やインタビュイーに共有しておいたり、カメラマンに撮影内容を共有したりする程度で済むことが多いですが、対談記事の場合は主役の2者にバランスよく話していただきながら、読者に趣旨を伝える必要があります。そのため事前に、構成案(プロット)とともに、台本をつくっておくケースがほとんどです。
対談の構成案は趣旨をしっかりふまえる
対談記事にはそれぞれ目的があるはずです。よくあるのが、「新サービスや施設の完成をアナウンスする」「就任の想いを伝える」「会社のブランド力を上げる」などでしょうか。構成案(プロット)作成にあたっては、これら目的が果たされることが“必要にして十分”。足りていないのはNGですが、余計な情報を盛り込みすぎるのもいけません。
新聞の対談記事の場合は、下記の流れで構成案を作ることが多いです。
構成案の作り方
- 構成案Aパターン…多くの対談にあてはまる構成
[過去を振り返る]→[現在を語る]→[未来を見据える]
両者にこれまでの経緯をふりかえってもらった上で、現状(強みや特色など)を語り合い、最後に今後どうしていきたいか想いを聞く、という流れです。 - 構成案Bパターン…伝えたい内容が多い場合に適した構成
[プロローグ]→[伝えたいこと①]→
[伝えたいこと②…]→[エピローグ]
対談によっては伝えたいことが複数ある場合も。そういうときは、いきなり伝えたいことに入るのではなく、前段で全体をくくるプロローグ(動機、経緯など)を挿入。その後、伝えたいことをまとめていき、最後にエピローグ(期待する効果、今後の展望など)を入れてしめくくる、という流れです。
想定される質問を作りゲストに投げかけ
構成案ができたら、それぞれの話のフックとなる質問を作っていきましょう。例えば、道路の開通を伝える対談で構成案Aを採用するならば、
想定質問の作り方
- 過去を振り返る質問例
「まずはこれまでを振り返りながら、開通の日を迎えた想いをお聞かせください」
- 現在を語る質問例
「今回の開通による整備効果、数値目標をお聞かせください」
- 未来を見据える質問例
「次の道路整備における重点エリアや、今後の課題があればお聞かせください」
など。インタビュー記事の場合は、質問を投げかけたまま当日を迎えることもありますが、対談記事では、二者それぞれがどのような回答をするか事前にすり合わせておき、対談当日に回答がバッティングしないように注意します。
台本(予定稿)を用意しておくと安心
対談する二者(多くの場合はその事務方)から、想定質問に対する回答が届いたら、それをもとに台本(予定稿)を作成します。対談までに時間がない場合は、想定質問+回答のリストをまとめておくだけでもよいでしょう。もし対談に登場するのがVIPなら、時間の有無を問わず台本を作成しておくことをおすすめします。
台本は、対談記事に関わる多くの人の安心材料になりますし、収録後のスピーディな初校アップにもつながります。原稿をオーダーするライターにお願いしても良いと思いますが、当社の場合は編集者が台本まで準備することがほとんど。対談の趣旨を深く理解している人が、ここまでの準備をするべきだと当社は考えます。
2.登壇者が満足するため対談当日も重要

さて、事前準備をぬかりなく行えましたか?先ほど「対談記事の成否は、事前準備にかかっている」と書きましたが、まだ油断してはいけません。対談当日にもするべき仕事はあります。
登壇者の話の強弱を確認
おそらく多くの対談は、みなさんが準備した構成案や台本に沿って進行することでしょう。しかし事前準備は、対談に登場する「本人」ではなく「事務方」を相手に、メールや電話のやり取りで進めることも少なくありません。だからこそ、対談当日は登壇する本人の表情や、話の力点に注目してください。
構成案や台本はあくまでも「素材」です。過信することなく、本番の様子に応じて追加や割愛、ブラッシュアップをして原稿を仕上げましょう。
事前準備の流れで当日の司会役を務めることも
対談当日は、司会役(ファシリテーター)が構成案や台本をもとに質問を投げかけます。媒体社が用意する場合は、地方局のアナウンサーやプロの司会者、新聞社の場合は主筆や論説委員、局長クラスがファシリテーターを務めることもあります。
対談記事の経験が多い当社の場合、ファシリテーターを任されることも。適切なタイミングで質問を投げかけ、ときに想定にはない質問を投げかけたり、時間にあわせて質問をカットしたりと、相応のむずかしさがありますが、対談企画への想いが強い場合は、自身で挑戦してみるのもよいと思います。
対談の写真撮影する際におさえておきたいこと
対談の司会役や、原稿を書くライターが別で手配されている場合、あなたは撮影ディレクションをするかもしれません(あわせてゲストの話の強弱をチェックすることは忘れずに)。以下に対談記事の撮影で必須な項目を挙げておきます。
対談記事で撮影する写真
- 対談中の登壇者
身振り手振りを交えた様子を、左右両方向から
- 対談中の二者をまとめて
逆八の字に向けたイスに座って二者を、まとめて1カットで
- 必要に応じて手元などのアップ
スタイリッシュな対談記事では、こういったクローズアップカットも
- 記念写真
企画で使用しなくても、必須の撮影カットです
なお「記念撮影」は、企画に使わなくても撮っておくことをおすすめします。対談終了後に主役の二名揃っての記念撮影を撮影するほか、場合によっては司会役をまじえた3名で、周りにいる事務方なども含めた大勢で、ということも。著名人との対談の場合は、記念撮影を数パターン行うこともあるでしょう。
初めて対談を行う企業の場合、記念撮影に気づかないこともあると思うので、「よろしければ記念に皆さんで写真を撮影されませんか」と声をかけるのも、あなたの腕の見せどころです。
3.対談後は「伝わる」記事に仕上げましょう

入念な事前準備から対談を終えホッとするのも束の間、いよいよ記事の仕上げに入ります。対談終了後に媒体社やライターとともに、仕上げ方の打ち合わせをしておくと間違いがありません。構成案や台本があるからといって、対談後の打ち合わせなしで取り掛かると、「あとで大直し」ということもありますので、当日を終え、早く“お疲れ様の一杯”を飲みたい気持ちは分かりますが、しっかりとすり合わせをしておきましょう。
台本があっても音声データは聞き直しましょう
対談中に録音した音声データは、文字起こしをしておきましょう。台本通り、脱線することなく進行したならば、当日のメモのみで文字起こしは必要ありません。しかし多くの場合は、当日ならではの話、補足などが出てきたはずです。
登壇者から「文字起こしデータをいただきたい」と言われることもあるので、文字起こしは面倒くさがらずに!
対談記事にあいづちは不要
長文になりがちな対談記事では、冗長な表現は避けた方が賢明です。登壇者のAさんが話した後に、Bさんが「そうですね」と言ったとしても、次の話題が同調する内容であれば、あえて「そうですね」と文字にしなくても伝わります。
また、司会役の「──最初に、あらためてこの日を迎えた想いをお聞かせください」は、文字数に限りがあるならば「──まずこの日を迎えた想いを。」でも済みます。このあたりは、企画の仕様にあわせてアレンジしましょう。
二者が話した内容のバランスは5:5を目指す
冒頭に書きましたが、対談記事の場合は登場する二者にバランスよく話していただくことが大切です。これは事前の構成案や台本、対談当日の司会役の腕にもかかりますが、片方が多く話すケースもあることでしょう。
美しいのは、二者が5:5のバランスで話すことですが、4:6ぐらいなら許されます。3:7以上の差が出てくるようなら、事前の台本には入れていたものの当日割愛された話題を足すなど、責任者や事務方と相談しながらバランスを取ってみるのも一案です。
話した内容が事実とは限らない
対談記事には、数字や日付、人物名、歴史的な事実など、いろいろなデータが出てくるかもしれません。本人が自信をもって発言したとしても、思い違いがあるかもしれまんので、ファクトチェックは必須です。複数の目でチェックし、場合によってはプロの校閲者を入れて、事実関係の確認は行いましょう。
当社もこのファクトチェックを重ねることにより、「しっかり見てくれている編集プロダクション」と評価いただいています。
4.対談記事の実例を紹介
中日新聞・「レゴランド・ジャパン・リゾート」2周年対談

☆レゴ認定プロビルダーとの対談でレゴのの魅力を再発信
開業2周年を記念した新聞記事広告で、レゴランド・ジャパンのトーベン・イェンセン社長と、レゴ認定プロビルダーの三井淳平さんとの対談を実施。事前準備はしつつも、当日のイベントの感想を盛り込んで、ライブ感のある記事内容に仕上げています。
中京綜合警備保障50年史

☆熱い想いと客観的事実を重ねながら発信
50年の歴史を会長のお言葉から熱く語っていただきながら、客観的な事実を重ねてまとめていった対談記事です。事前準備を整えた後は、地元テレビ局のアナウンサーに司会役を務めていただき、やわらかい語り口で想いを引き出していただきました。
朝日インテック・オウンドメディア「WAYS」

☆医療情報は綿密なファクトチェックが必要
カテーテル治療用の医療機器で世界中の医療関係者から注目を集める「朝日インテック」のオウンドメディアで、手術支援ロボット「ダヴィンチ」のパイオニアとして活躍されている藤田医科大学の宇山教授と、同社の宮田代表との対談を実施。
事前準備においては、朝日インテックの業容や経営計画、宇山教授の著書にも目を通し、台本づくりを行いました。医療情報ということで原稿執筆の際のファクトチェックも入念に行い、大きな修正もなくサイトアップとなりました。
中日新聞・Aichi Sky Expo開業記念知事対談

☆多忙な知事のスケジュールにあわせ当日に質問をアレンジ
中部国際空港に直結する大規模展示場「Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)」の開業を記念し、モルガン代表と、愛知県の大村知事の対談を実施。
知事が対談に割ける時間が当日に決まったこともあり、事前質問の調整や、話を切り上げていただくタイミングなど、かなり難易度の高い企画となりました。イレギュラーは想定されたものの、やはり事前準備を行っておくことで、当日の変更対応もスムーズになった好例です。
中日新聞・長者町再開発座談会

☆話者が多い座談会はコメントのバランスに注意
こちらは対談記事ではなく、座談会記事になりますが、進行方法は変わりません。特に注意をしたいのが、話者のコメントのバランスです。
この企画の場合は、全員の発言回数を揃えながら、首長である市長に最後の言葉をいただくことで、企画がしっかりと締まりました。
中部電力・子育てメディア「COELOG」

☆ロケーションを活かしてバラエティに富んだ撮影を実施
中部電力が地域の子育てをサポートするための情報サイト「COELOG」で、日本総合研究所主任研究員の池本美香さんと、地域の課題を住民自らが考えて解決するためのコミュニティデザインを提唱するstudio-L代表の山崎亮さんの対談を実施。
テーマが子育てということで、やわらかでスタイリッシュなデザインモチーフのWebサイトにあわせ、対談当日は撮影にも工夫。同じ会場で座る場所を変えて撮影するなどして、バラエティに富んだ写真を撮ることができました。
5.対談記事のまとめ
いかがでしたか?対談記事に費やすカロリーの高さにびっくりされたかもしれません。事実、対談記事を「おまかせ」で作ることができる編集者、編集プロダクションは限られており、だからこそ当社も高い頻度でお声がけいただいている状況です。
ぜひ皆さんも、インタビューとは異なる対談記事ならではのノウハウを身につけ、できる企画の幅を広げてみてください。もちろん、お困りでしたらお気軽に当社にご相談ください。
関連記事
新着記事
人気記事
お問い合わせ
お仕事のご相談や、採用についてなど、
お気軽にお問い合わせください。